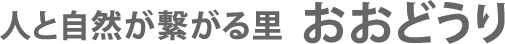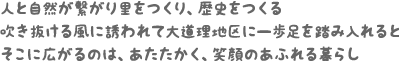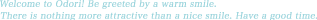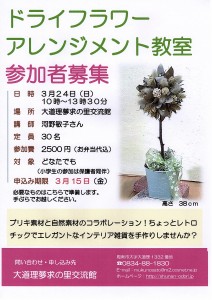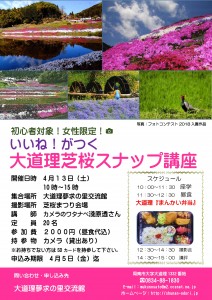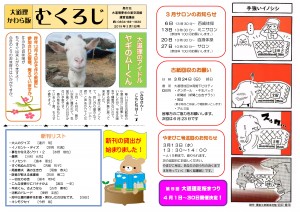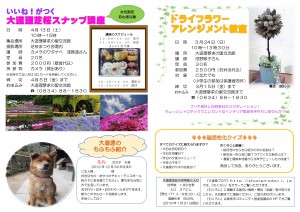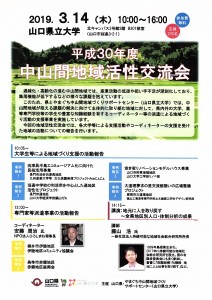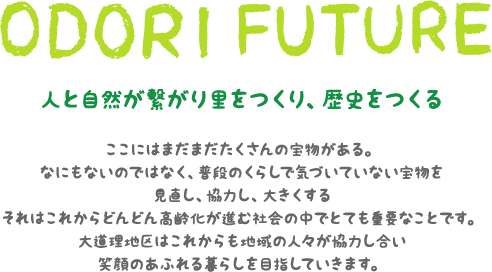こんにちは。3月とは思えない暖かさですね。
3月4日ガーデニング教室が開催されました。
米沢園芸の田村先生の楽しいお話しで、笑い声が広がりました。
かわいい多肉植物の寄せ植え?今回は楽しめるようにと花が咲くものを持ってきて下さいました。
ポットから出した苗の根をカットし(根はまた伸びます!)いくつかの苗を中心におしくらまんじゅうで植えるのがコツ!
横から見ると半円状になるように、中心は高くします。
育て方は、今回はガラスの器なので、窓越し日陰がGood!
教室終了後には、恒例の質問コーナー❕ 色々な質問が飛び交いました。
紫陽花の剪定は? 花が咲き終わった後1年に1回、赤い花は家の周りに、青い花は庭に、白い花はどこでもOKですよ。
河津さくらの花が咲かないのはなぜ? 植える時に根を洗ってえば、花が咲きます。
たくさんの方々にご参加いただき、ありがとうございました。
24日はドライフラワーアレンジメント教室開催があります。ぜひお越しください。
いいね!がつく 大道理芝桜スナップ講座を開催します。
初心者対象・女性限定です。
講師にカメラのワタナベ淺原透さんをお迎えします。
スマートフォンの上手な撮影方法も教えて頂けますよ。
ぜひ、ご参加ください。
こんにちは。今日は春を感じさせるような陽気ですね。
さて、『第9回大道理芝桜まつり』の開催が決定しました。開催期間は4月1日から30日です。
暖冬で開花が例年より早いのかな……?と思う人間様を横目に、芝桜の発育状況は今のところ例年と変わりません。
開花状況は、お伝えしていきますので、しばらくお待ちください❀
こんにちは。ヤギのムーです? もうすぐ1歳です。
昨年の5月に大道理の瀬戸兼に来ました!
雪が降る日や寒い日は、大道理小学校の小屋にいます。
ムー君と声をかけてもらうと嬉しいです♡
お天気のいい日☀に会いに来てね。待ってるよ~ メェ~~~
こんにちは。3月24日、大道理夢求の里交流館主催のドライフラワーアレンジメント教室を開催します。
今回は、❀❀ブリキ鉢とドライフラワーのコラボレーション❀❀おしゃれなインテリア雑貨を手作りします。
大道理の春を感じに、ぜひお越しください。お待ちしております。
3月4日、大道理夢求の里交流館主催のガーデニング教室を開催します。
ぷっくりとした葉がかわいらしい多肉植物の寄せ植えです。素敵なアレンジアイデア!水やり、管理などを米沢園芸の田村先生から楽しく教わります。
お申込み・お問い合わせは交流館までお電話ください。
皆様のお越しをお待ちしております。